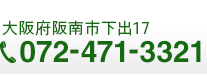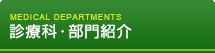医療安全管理室
医療安全のための指針
1.総則
1-1.基本理念
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。当院においては院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取り組みを要請する。
AIFフィロソフィーの中でも「当然のゼロ」=「トラブル・ミスはゼロで当然」という言葉で明文化されているところである。また、患者と医療提供者は「パートナー」と「チーム」という考え方において、患者の安全を第1に患者と同じ視線にたった医療を心がける必要がある。
1-2.用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下の通りとする。
(1)医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象
医療提供者の過失や産むは問わず、不可抗力と思われる事象も含む
(2)当院
社会医療法人生長会 阪南市民病院
(3)職員
当院に勤務する医師、歯科医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む
(4)医療安全管理者
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、院長により、当院全体の医療安全管理を中心的に担当する者
1-3.組織および体制
当院における医療安全管理対策を患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当院に以下の役職および組織等を設置する。
(1)医療安全管理者
(2)医療安全管理委員会
(3)医療に係る安全確保を目的とした報告
(4)医療に係る安全管理のための研修
2.医療安全管理委員会
2-1.医療安全管理委員会の設置
当院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために医療安全管理委員会を設置する。
2-2.委員の構成
(1)医療安全管理委員会の構成は以下の通りとする。
医療診療部、看護部、薬剤部、診療技術部、事務部門の責任者を配置し、以下を含む。
①副院長
②看護部長
③医療安全管理者
④医薬品安全管理者
⑤医療機器安全管理者
⑥医療放射線安全管理者
(2)委員の氏名および役職は公表・掲示して当院の職員およびパートナー等の来院者に告知する。
(3)委員長に事故あるときは副院長がその職務を代行する。
2-3.任務
医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う。
| (1) | 医療安全管理委員会開催および運営 |
| (2) | 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた事象の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知 |
| (3) | 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案 |
| (4) | その他、医療安全の確保に関する事項 |
2-4.委員会の開催および活動の記録
| (1) | 委員会は原則として、月1回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が招集する。 |
| (2) | 委員長は、委員会を開催したときは速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管する。 |
| (3) | 委員長は委員会における議題の内容および活動の状況について、必要に応じて院長に報告する。 |
3.報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
3-1.報告とその目的
この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。具体的には①当院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事象等を検討し、医療の質改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること、②これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とする。これらの目的を達成するため、すべての職員は次項以下に定める要領に従い、医療事故等の報告をおこなうものとする。
3-2.報告にもとづく情報収集
(1)報告すべき事項
すべての職員は、当院内で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、概ねそれぞれに示す期間を超えない範囲で速やかに報告するものとする。
| ① | 医療事故 →医療側の過失の有無を問わず、パートナーに望ましくない事象が生じた場合は、発生後直ちに所属長へ。所属長からは医療安全管理者や院長へと報告する。 |
| ② | 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れればパートナーに有害な影響を与えたと考えられる事象 →速やかに所属長または医療安全管理者へ報告する。 |
| ③ | その他、日常業務のなかで危険と思われる状況 →適宜、所属長または医療安全管理者へ報告する。 |
(2)報告の方法
| ① | 前項の報告は、院内医療安全管理システムに入力して行う。事象レベル3以上・および緊急を要する場合は、ひとまず口頭で報告する。パートナーの救命措置等に支障が及ばない範囲で、遅延なく医療安全管理システムで報告する。 |
| ② | 報告は、診療録・看護記録等、自らがパートナーの医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。 |
| ③ | 自発的報告がなされるように匿名で報告することができる。 |
3-3.報告内容の検討等
(1)改善策の策定
医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から当院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする。
(2)改善策の実施状況の評価
医療安全管理委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
3-4.その他
| (1) | 院長、医療安全管理者および医療安全管理委員会の委員は、報告された事例について職務上知り得た内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。 |
| (2) | 本校の定めにしたがって報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。 |
4.安全管理のための指針・マニュアル整備
4-1.安全管理マニュアル等
安全管理のため、当院において以下の指針・マニュアル等(以下「マニュアル等」という)を整備する。
(1)院内感染対策指針
(2)医薬品安全管理業務手順書
(3)輸血マニュアル
(4)褥瘡管理マニュアル
4-2.安全管理マニュアル等の作成と見直し
(1)上記のマニュアル等は、関係部署の共通のものとして整備する。
(2)マニュアル等は関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。
(3)マニュアル等は、作成、改訂のつど、医療安全管理委員会に報告する。
4-3.安全管理マニュアル等作成の基本的な考え方
| (1) | 安全管理マニュアル等の作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、パートナーの安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。 | |
| (2) | 安全管理マニュアル等の作成、その他、医療の安全、パートナーの安全確保に関連する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。 |
5.医療安全管理のための研修
5-1.医療安全管理のための研修実施
| (1) | 医療安全管理委員会は、あらかじめ作成した研修計画に従い、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。 |
| (2) | 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。 |
| (3) | マニュアル等は、作成、改訂のつど、医療安全管理委員会に報告する。 |
| (4) | 病院長は、本指針『5-1』(1)号の定めにかかわらず、当院内で重大事故が発生した後など、必要があると認めるときは、臨時に研修を行うものとする。 |
| (5) | 医療安全管理委員会は、研修を実施した時は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。 |
5-2.医療安全管理のための研修実施方法
医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。
6.事故発生時の対応
6-1.救命措置の最優先
医療側の過失によるか否かを問わず、パートナーに望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず、当院内の総力を結集して、パートナーの救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
また、当院内のみでの対応は不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
6-2.院長への報告など
| (1) | 事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。 パートナーが事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。 |
| (2) | 説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療録、看護記録等、自らがパートナーの医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。 |
7.その他
7-1.本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全管理者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。
7-2.本指針の見直し、改正
(1)医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
(2)本指針の改正は医療安全管理委員会の決定により行う。
7-3.本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員はパートナーとの情報の共有に努めるとともに、パートナーおよびその家族等から閲覧の求めがあった場合にはこれに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理者が対応する。病院ホームページで閲覧することができる。
7-4.患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。
【改訂履歴】
| 第1版 | 2015年4月1日 | 制定 |
| 第2版 | 2016年3月1日 | 定期検査の整合性に伴う改訂 |
| 第3版 | 2017年7月12日 | 定期検査 |
| 2018年4月12日 | ホームページ用の医療安全のための指針を掲載 | |
| 2019年5月19日 | 定期検査 | |
| 2021年7月21日 | 定期検査 | |
| 2022年8月 1日 | 定期検査 | |
| 第4版 | 2023年11月 1日 | 内容改訂 |